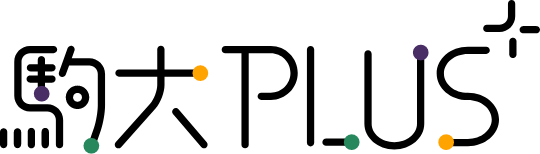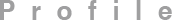2025.03.19
2025.03.19

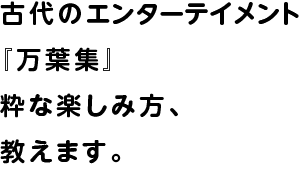
新元号「令和」の発表とともに『万葉集』が注目を浴びている。そこで今回は、『万葉集』を専門に研究している中嶋先生に、『万葉集』の編纂者と言われる大伴家持とその父、旅人を中心に読みどころをうかがった。男と女の恋愛模様や仕事の苦労など、今も昔も変わらない人々の喜怒哀楽を、気軽に楽しんでみてはいかがだろう。
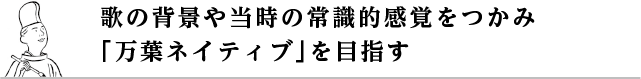 歌の背景や当時の常識的感覚をつかみ
歌の背景や当時の常識的感覚をつかみ
「万葉ネイティブ」を目指す
私にとって『万葉集』のおもしろさの一つは、"整然としていないカオスの世界"にあります。『万葉集』は、多くの巻に部立があり、テーマの方向づけがなされています。また歌だけでなく、題詞や左注に、詠まれた場所や背景、作者などの情報が添えられていることもあります。そうした情報と歌とを合わせて、当時の人々の暮らしぶりや思いを読み解いていきます。
なかには、歌の背景がまったく記されていないものや、対になるべき歌が欠けていることもありますが、そこに理由もあるのでしょう。なぜ、その歌が残ったのかを推理することも一つの楽しみです。『万葉集』は単なる事実の羅列ではありませんから、少し想像力を羽ばたかせて解釈してもよさそうです。そこに尽きせぬおもしろさがあり、読めば読むほど、新しい発見があるのですね。
私も学生のころは、歌の形式や、『万葉集』がいかに享受されてきたか、その変遷をたどるなど、先人たちの研究の隙間を探して深掘りしようとしたこともあったのですが、大学で教鞭をとるようになって、ゼミなどで学生と作品を読みこんでいくうちに、歌の背景をなす文化や自然、当時の人たちの常識であったであろうことを踏まえて、テキストそのものをじっくり読み解くおもしろさと、作品自体の深さに改めて気づかされました。そのような場を創出してくれた歴代の学生たちには感謝以外、言葉がないですね。
歌をありのままに受け止め、できうる限りこちらから歩み寄って、当時の人なら分かったであろう感覚を身につける、言うならば、「万葉ネイティブ」になることを目指す感じです。

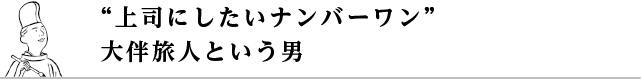 "上司にしたいナンバーワン"
"上司にしたいナンバーワン"
大伴旅人という男
このように読んでいくうちに、気になる歌人が出てきます。ここでは、大伴旅人と家持の親子を例にお話ししましょう。家持は『万葉集』の編纂者と考えられています。
大伴旅人は、「令和」で話題になった梅花宴を、長官になっていた大宰府で開催した人物です。『万葉集』に70首ほどの歌が残されており、その詠作は60歳以降のものばかりです。
その中に13首連続して酒を讃美する「讃酒歌」と呼ばれる歌群があります。『万葉集』には酒をほめる歌はほぼないので、いつの間にか旅人は酒飲みキャラに仕立てられてしまったようなところがありますが、これでは、あまりに短絡的です。
もちろん彼も、そこそこにお酒はたしなんだでしょう。しかし、讃酒は中国の詩文に見られる発想で、それを観念的に日本の歌の形で、おそらく宴会という場に合わせて詠んだのだと思います。
旅人の歌をたどっていくと、仲間や部下に囲まれ愉快に歌もやりとりする、良き上司としての姿が浮かんできます。その想像される姿からは"上司にしたいナンバーワン"なのではないかと思えてきます。
例えば、旅人が派遣先の大宰府から都に戻る際、部下たちが送別の宴を開きます。そこで部下の一人の大伴四綱は、月夜よし 河音清けし いざここに 行くも去かぬも 遊びて帰かむという歌を詠みます。「月は美しい。川の音もよどみない。さあ、ここで、都に行く人も行かない人も、遊び(ともに大宰府へ)帰りましょうよ」と部下の方から、都へ帰ってほしくない気持ちを伝えたのです。また、親しくなった遊行女婦(貴族たちの宴席で古歌や舞を披露する女性たち)から贈られた別れを惜しむ歌も残っており、年齢など感じさせず、なかなかモテたようです。
旅人には、大宰府に同行したもののすぐに亡くなった妻のことを詠んだ歌もあります。旅人は大宰府から都へ戻る際、随所で亡き妻を偲び歌にしました。そして家に着き、庭を見たとき、吾妹子が 植ゑし梅の樹 見るごとに 情むせつつ 涕し流ると詠みました。そこまでの歌には詠まれなかった涙が、以前と変わるところのない家に着いた途端にこらえきれずに、流れゆくさまが詠まれているのです。60代後半の男性が流す涙です。
『万葉集』の中には旅人が亡くなったときの歌も残っています。しかし、彼と親しかった人々が彼の死について詠んだ歌は一首もありません。考えてみれば、人は本当につらいとき、その感情を歌に託すことなどできないのではないでしょうか。沈黙の悲しみを感じ取ればいいのだと思います。
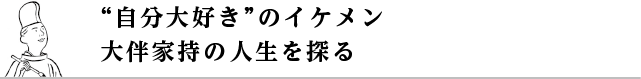 "自分大好き"のイケメン
"自分大好き"のイケメン
大伴家持の人生を探る
旅人の息子、家持は『万葉集』を通して若い頃からの生き方を垣間見ることができます。『万葉集』には家持の短歌や長歌が450首以上収められていて、これは『万葉集』全体の歌の1割を超える数です。『万葉集』は家持とともに立ち現われるといってもおかしくありません。しかも、歌を読むと、自分に注目してほしい典型的な"自分大好き"タイプに見えてきます。名門大伴氏の嫡流で、官僚としては20代にして越中国(今の富山県)のトップを任され、彼の父や祖父と同じく、いつかは大納言になると信じて生きてきたと思われます。
家持の『万葉集』歌人としてのデビューは数えで16歳、つまり現代の15歳です。ふりさけて 三日月見れば 一目見し 人の眉引き 思ほゆるかも三日月を見ると、一目見たあの人の眉が思い出されるというのです。「見し」という過去の表現が実にいいですが、以前の交際相手の存在をにおわせるのです。越中に行くまでの家持の歌の多くは、様々な女性との交際を感じさせる歌です。自分の歌を載せないで、相手の歌のみを載せるようなこともしています。モテる男としてプロデュースされた家持を私たちは受け止める必要があるでしょう。きっと相当なイケメンだったのでしょうね。
そんな家持を歌で翻弄した人物がいます。彼の正妻、大伴坂上大嬢です。彼女は、旅人の異母妹で、家持の叔母にあたる大伴坂上郎女の娘です。坂上郎女は『万葉集』の女性の歌人では最も多くの歌を残す人物でした。母も旦那も歌が好きという環境で、坂上大嬢の歌のスキルは相当に向上しそうですが、現実はそうではなかったようです。
彼女は家持に玉ならば 手にも巻かむを うつせみの 世の人なれば 手に巻きかたしと贈りました。「玉だったら手に巻けるのに、この世で生きている人だから手に巻けない」という内容です。「家持が玉だったら、いいのに」と詠んでいるのです。基本的には男性から女性に歌を詠むのですが、この歌は彼女から詠みかけているようです。しかも「玉」は宝玉類を表しつつ、女性の比喩として用いられるのが常でした。家持は「俺は玉なのか...」とルールに囚われない彼女に困惑したことでしょう。でも我が思ひ かくてあらずは 玉にもが まことも妹が 手に巻かれむをと、「こんなことなら玉になりたい、手に巻かれたい」と否定することなく応じてしまう家持は、優しいともいえそうですし、彼女に心底惚れているともいえそうです。
このように歌は当時のモテる男のたしなみの一つでした。現代のインスタグラムやLINEでのメッセージのやりとりのように、歌はコミュニケーションを楽しむツールといえます。恋愛のかけひきを探る気持ちで読み解けば、『万葉集』はぐっと身近に感じられるでしょう。
なお、リア充を満喫しているかのような家持ですが、『万葉集』の最後の歌は、40代前半のものです。家持はその後20年以上は生き、政治家としての活動は『続日本紀』を通じて把握できますが、歌人としての活動はどうなったのかよく分かりません。藤原氏が躍動する中、政治家としては不遇でした。大納言になれず、父、祖父の偉大さ、そして時代の合わなさも感じていたでしょう。『万葉集』はそのような悲しい家持をあまり見せようとはしません。
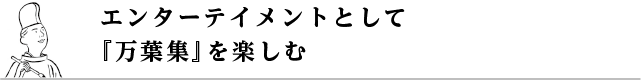 エンターテイメントとして
エンターテイメントとして
『万葉集』を楽しむ
ほんの一部を紹介したにすぎませんが、このように、『万葉集』は当時の人々が織りなすエンターテイメントに他なりません。なぜそこまで五・七・五・七・七は人々を魅了し続けてきたのか、その答えを一言で述べるのは困難ですが、おもしろかったから、楽しかったからという側面は大事にしてよいでしょう。まさにエンターテイメントなのです。
これまで私たちは、『万葉集』をはじめとした多くの古典文学を、研究という名のもとであまりにも真面目に読みすぎてきたのかもしれません。いっそ、テレビの連ドラやバラエティなどを見る気分で、いろいろとザッピングして好みのものを見つけ、少しずつ掘り下げてみてはどうでしょう。恋バナが好きか、泣けるドラマが好きか、お笑いが好きか、推しの歌人は誰か。古代の人々を魅了したものには、現代の我々にも共感できる部分がたくさんあるはずです。
もちろん、的確な読解が前提であり、基本ですが、その上で、想像力をたくましくはばたかせ、このようなことが繰り広げられているのではないか、背景にこのようなことがあるのではないか、と妄想すること、それを時に仲間と語り合うことは、貴重な体験に思えます。
しかし、今と大きく違うところもたくさんあります。古典文学は視覚を重視した表現がどうしても多くなります。それだけに電気やガスのない時代ゆえ、月明かりと星をのぞけば、夜が真っ暗だったということは、留意しておきたいですね。聴覚を鋭敏にさせることもありますし、月を頼りに出かける男性、それを待つ女性といったように様々なドラマは夜に展開されていたわけです。
作品に丁寧に向き合いながら、当時の感覚を身につけ、想像する力を大事にして、エンターテイメントとしての『万葉集』を楽しんでもらいたいなあと思います。

- 中嶋真也教授
- 東京大学大学院博士課程修了。博士(文学)。2004年、駒澤大学文学部国文学科専任講師。2014年より同教授。『万葉集』を中心に飛鳥~奈良時代の文学を研究する。主著に『コレクション日本歌人選 大伴旅人』(笠間書院)、『大学生のための文学トレーニング 古典編』(共著・三省堂)、『和歌のルール』(共著・笠間書院)など。
関連記事 - 「ラボ駅伝」カテゴリーの新着記事
 2025.03.19
2025.03.19
 2025.02.03
2025.02.03
第32区 仲田資季准教授『プラズマの渦と流れの物理と数理』
 2024.04.10
2024.04.10
第31区 近衞典子教授『上田秋成から見る近世文学』
 2024.03.05
2024.03.05