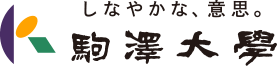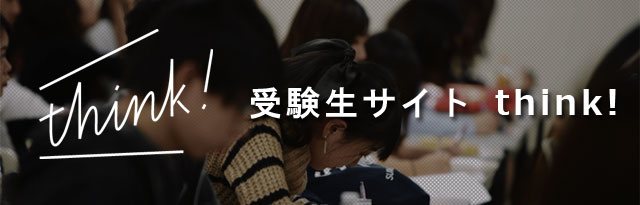~襷~ 『よい』環境の魅力を見出し、広げる。〜広告で人と教育をつなぐ~
【襷(たすき)】は、駒澤大学に通う皆さんが「どのような社会人生活を送りたいか」をイメージできる、キャリアセンター発の連載企画です。在学生が現在活躍する駒大OB・OGを訪問し、先輩たちのリアルな声をお届けします。
大橋友里絵先輩に、文学部3年 市村が取材しました!(2025年3月取材)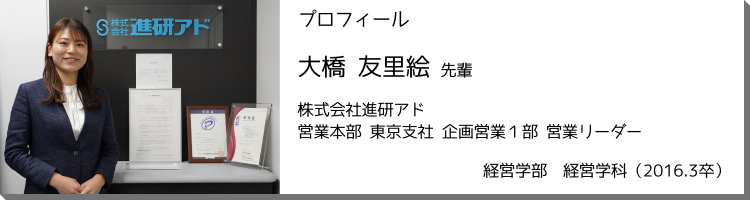
学生時代の学びとチャレンジ
なぜ中村公一先生のゼミを選んだのですか?
実はもともと駒澤大学の他に志望している大学がありました。その分入学後は大学の中でより挑戦し、自分自身が成長できるきっかけを探していました。そんな中、ゼミを選んだ理由は二点あります。
一点目は中村公一先生の授業の面白さに吸い込まれたことです。先生は身近な人気漫画の例を用いるなど、学生の目線からでもわかりやすく経営学を教えてくれました。
もう一つは自分を成長させるために「あえて厳しい環境に身を置きたい」という思いからでした。結果的にこの選択は正解でした。
ゼミではどのような活動をされていましたか?
経営戦略論を専攻し、中村公一先生のゼミで副ゼミ長として活動していました。このゼミでは頻繁にプレゼンテーションを行い、業界に関する調査から相手に発信するアウトプットまでを徹底的に学びました。研究テーマはグループ単位で設定し、例えば化粧品業界や飲料業界などを経営学的視点から分析します。
ゼミでは個人で調べた内容をもとに、グループでプレゼンテーションを競い合う形式で発表していました。毎回グループメンバーが変わるため、リーダーを務めたり、フォロー側にまわったりとさまざまな経験をしました。
また、実際に企業の方に対して学生視点からプレゼンテーションを行う経験もさせていただく機会がありました。
ゼミ活動で身についたスキルは今の仕事に活きていますか?
仕事に直結しています。プレゼン能力はもちろん、論理的思考力や分析力、検証力も養われました。自分の考えを仮説として立て、それを相手に伝える力は、広告業界で欠かせない能力です。データに基づいて意見を整理し、課題解決に向けて提案するという今の仕事のスタイルは、ゼミでの経験が基盤になっています。
特に印象深いのは、ゼミ発表に向けた準備の過程です。チームメンバーと同じ目標に向かって議論を重ね、一つのものを作り上げる経験をしました。就職活動では「傾聴力が身についた」と自己PRしていましたが、まさにその言葉の通りの成長実感があります。
もちろん傾聴力だけではなく、臆せず自分の意見を発言したり、目線合わせを行う力など、今のビジネスに必要な力の多くがゼミ活動を通して培われたと感じています。
学生時代に他にどんな活動に力を入れていましたか?
学生時代はゼミだけでなく、サークル活動にも幹部として力を入れていました。学外では、某有名カフェ店でアルバイトをしながら新人研修にも携わりました。この経験も人材育成や組織マネジメントの基礎を学ぶ貴重な機会となりました。
大学4年間を通じて身についた最も重要なスキルは、場面によって自分の役割を変える柔軟性です。リーダーとしてチームをけん引することもあれば、ファシリテーターとしてサポート役にまわることもあります。その使い分けができるようになったのも、様々な立場を経験した大学生活のおかげです。
様々なバックグラウンドを持つ仲間との出会いも大きな財産になりました。宮崎や長野など遠方から来た学生も多く、それぞれに異なる価値観や目標を持っていました。そのような多様性のある環境で、共通の目標に向かって努力することで、深い絆が生まれました。今でも結婚式に呼び合うほどの関係が続いています。
就職活動の選択と決断
どのように業界を見ていましたか?
働くことを想像したときに、自分の「好き」という感情と、社会の何かに役立つのかという点を掛け合わせて考えていたため、広い視野を持って多くの業界を見るようにしていました。広告業界だけでなく、化粧品業界やカード会社、旅行会社など広く見ていく中で、自分の本当にやりたいことを絞り込んでいくようにしていきました。
その過程で、自身の大学受験での経験や、ゼミで学んだ知識を活かしながら、高校生に「この大学の素晴らしい点はここだよ」と高校の3年間で気づくきっかけを発信したい、という思いが強くなりました。そこで現在の広告と教育の両輪で世の中に貢献できる進研アドへと入社を決定しました。
前記したように自分自身の経験から、大学選びの重要性を痛感していたので、その過程で高校生をサポートできる仕事に魅力を感じたのです。
就職活動を通じて学んだことはありますか?
大学受験の挫折経験もあり、就職活動は自分の人生を変えるタイミングだと考えていました。だからこそ後悔のないように取り組み、多くの説明会やエントリーシートの提出、面接練習を重ねました。
2016年卒の就職活動は長期戦だったため正式に内定が決まったのは8月頃と、活動期間は長かったですが全力で取り組んだ充実感がありました。
振り返ると、大企業の名前だけで判断するのではなく、福利厚生や働き方など、自分に合った環境を総合的に見極めることの大切さを学びました。OB・OG訪問などを通じて、実際にそこで働くイメージを持つことも大事だと実感しています。
また、取り組む前から諦めるのではなく、可能性を信じて挑戦することの大切さも学びました。
社会人としての歩みと挑戦
現在の仕事内容について教えてください
2016年に入社し、今年で10年目を迎えます。入社当初から変わらず東京の営業部門で働いており、現在は営業リーダーの役割も担っています。
主な業務は高等教育機関、つまり大学や短大、大学院や専門学校などの顧客の学生募集支援です。例えば、大学が入学者を多く集めるためにはその大学ごとの課題をあぶりだし、どのように解決していくことが必要か、そのためにはどのような広告で何を伝えたら高校生や保護者に響くのか、魅力的に感じてもらえるのか等を提案しています。最近では大学の新設改組に関する改革支援や、教育改革の支援にも携わっています。
高等教育に特化した広告会社を選んだ理由は何ですか?
現在の会社を選んだ理由は、自身の大学受験の経験に深く関わっています。私自身、受験時の挫折を経験した後、4年間を経て駒澤大学の良さに気づくことができましたが、「もっと早くからこの大学の良さに気づけるタイミングがあれば」と考えたとき、高校生が自分に合った大学を見つける手助けがしたいと思いました。
高校生に新しい気づきや発見を届けられる仕事に魅力を感じました。飲料や化粧品など幅広い業界と関わる広告会社も検討しましたが、高等教育に絞って働くことで、より自分自身がワクワクできると考えたのです。
駒澤大学の魅力をどのように感じていますか?
駒澤大学の大きな魅力は、ワンキャンパスで多様性のある学生が交わる環境だと思います。他大学では学部ごとにキャンパスが分かれていることも多いですが、駒澤大学ではさまざまな学部の学生が同じ場所で学び、交流しています。
私自身もサークル活動を通じてグローバル・メディア・スタディーズ学部や医療健康科学部の学生とも仲良くなりました。こうした多様なバックグラウンドを持つ学生との出会いが、視野を広げる機会になります。自立しつつも協調性を持つ学生が多いのも特徴ではないでしょうか。
また、魅力的な教職員が多いことも駒澤大学の強みです。中村公一先生のような個性的で学生の成長を本気で考えてくれる教員との出会いは、大学生活を豊かにしてくれます。こうした一人ひとりの魅力を外部にもっと発信していくことで、駒澤大学の価値をさらに高められると思います。
業務の中でのやりがいは何ですか?
やり取りするお客様は大学の入試広報部署の方が多いため、大学行事や出願期間前は忙しくなります。そのため特に夏から秋にかけては繁忙期となりますが、チームで協力して乗り切っています。
一方で、複数のプロジェクトを同時進行させるセルフマネジメントの難しさもあります。様々な顧客に対して進捗頻度が異なるため、それぞれのコントロールが必要です。ただ、弊社は一人で抱え込むのではなく、チームで解決していくという文化があるので、その点は安心感があります。
このような慌ただしい日々の中でやりがいを感じるのは、新しい企画が採用されたときだけでなく、私を通して会社が信頼されていると感じる瞬間です。お客様がこれまでになかった発想や新しい視点に「やってみたい」と気持ちを変えてくださる時、信頼関係が築けていると実感します。そうした瞬間が、この仕事を続ける大きなモチベーションになっています。
営業活動で大切にしていることは何ですか?
特に意識しているのは「自分一人ではなく、会社の窓口として責任を持つ」という点です。その場だけ良ければいいのではなく、これからも長くお付き合いいただくために、より良い関係を築くためのコミュニケーションを心がけています。
お客様が知りたい情報を求められる前に先に共有したり、レスポンスを迅速に行ったりすることも当然ながら重視しています。また、社内のコミュニケーションも非常に大切にしています。営業は様々な部署と関わりますが、そのやり取りが円滑であればあるほど、お客様へのより良い提案やプレゼンテーションが可能になります。
タスク管理に追われてしまうことはないですか?
スケジュールを逆算して余裕を持って依頼することも心がけています。例えば、2週間後のお客様への提案に向けて、その前に社内での打ち合わせを設定し、さらにその後の資料作成期間も考慮してタイミングを計っています。
余裕を持ったスケジュール管理は、自分自身の精神的な余裕にもつながり、依頼を受ける側も気持ちよく仕事ができるからです。
広告業界の課題と将来性についてどう考えていますか?
広告という仕事は「絶対になくてはならないものではない」という特性があります。そのため、将来性を考えると、どれだけ必要とされるものであり続けるかが重要な視点であると感じています。
また、広告業界の特徴として、一人では何もできないという点があります。企画を立てる営業、アイデアを形にするクリエイター、それを制作・印刷する会社など、様々な専門家が集まって初めて一つの広告が完成します。この連携は難しさもありますが、だからこそ柔軟なコミュニケーション能力が重要になると考えています。
リーダーシップとキャリア構築
チームリーダーとしてどのようなマネジメントを心がけていますか?
現在の部署では、4~5人のチームを率いています。部全体では10人程度で、部長の下でリーダーとして活動しています。リーダーとして、新入社員や若手社員とのコミュニケーションを大切にしています。
特に1年目や2年目の社員には、つまずかないように定期的に時間を取って、1週間の予定や進め方を一緒に考えています。自分からの情報発信が得意ではない社員に対しては、部会という週1回の集まりの場で、今月の動きや来週に必要な対応などを積極的にヒアリングするようにしています。
新卒社員が早く成長するために必要なスキルは何でしょうか?
新卒で活躍している若手社員に共通しているのは、報告・連絡・相談がしっかりしていることです。1年目は分からないことが多いのは当然ですが、それでも自分の考えを巡らせ、必要なときにすぐに相談できる人が成長しています。
一人で解決できない問題があっても、すぐに相談してもらえれば、複数人で解決策を考えることができます。そうすることで業務が停滞せず、スムーズに進められるのです。もちろん個人のポテンシャルがある人もいらっしゃいますが、基礎基本がしっかりできている人が成長する傾向にあります。
入社時に私自身が困難に直面した際に重視したのは、なぜできなかったのかを振り返ることです。提案が通らなかったら理由を深く考え、再考し、お客様に直接意見を伺うこともありました。次に活かせるよう、足りなかった部分を明確にする姿勢が大切だと実感しています。
これからのキャリアプランについてどのようにお考えですか?
会社の中で自分がどう成長し、どう貢献できるかを考えています。現在のポジションでの経験を活かしながら、これからも担当するお客様の課題解決に取り組んでいきたいです。
女性としてライフスタイルが変わる可能性はありますが、そんな時でも何らかの形でお客様と関わる部署で働きたいと考えています。
実際に弊社には育休から復帰したママ社員が多く、営業のサポートや戦略立案部署など、様々な形で活躍しています。フレックス制度や在宅ワークなど、働き方の柔軟性も確保されています。こうした仕組みが、長く同じ会社で働きたいと思える理由の一つになっています。
後輩たちへのメッセージ
駒澤大学の学生は現状に満足せず、「もっとこうしてみよう」という意欲を持った人が多いと感じています。
大学生活をより有意義にするのは自分次第です。自分の行動や気持ち次第で変えられますし、それをサポートしてくれる環境が駒澤大学にはあります。安心して学業に取り組み、自分の可能性を広げてほしいと思います。
何事にも全力で取り組み、自分がワクワクすることに向かって走ってください。そうすれば必ず素晴らしい大学生活と、その先の未来が広がっていくはずです。4年間はあっという間ですが、その時間を最大限活用することで、卒業後の長い人生に活きる力を身につけることができます。
おわりに~インタビュアーの感想~
今回の取材を通じて、大橋先輩が「環境の価値」をいかに見極め、活かしてこられたかという点に深く感銘を受けました。特にゼミを選んだ理由として「あえて厳しい環境に身を置きたい」と語られた言葉には、環境を主体的に選ぶ大切さを教えられました。
私自身も就職活動中で様々な業界を見ている最中ですが、先輩が「自分の好き」と「社会への貢献」を掛け合わせて高等教育に特化した広告業界を選ばれた経緯は、業界選択の新たな視点を与えてくれました。特に、自身の大学受験の経験から「もっと早くこの大学の良さに気づけるきっかけを作りたい」という思いで進路を決められたことは、仕事選びに「自分ならではの理由」があることの大切さを教えていただきました。
「自分次第で変わることができる」という言葉は、これからの就職活動や人生の岐路に立ったときに思い出したいと思います。貴重な時間をいただき、本当にありがとうございました!
[著]・[聞] 文学部 社会学科 社会学専攻3年_市村瑠菜
[写] キャリアセンター_山口魁紀
※記事の内容は取材時点のものであり、最新の情報とは異なる場合があります。
※本記事掲載写真は、無断での転載・使用はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
本記事関連リンク
株式会社 進研アド
駒澤大学経営学部経営学科
駒大PLUS | 中村公一教授 『M&Aと組織マネジメント』
襷~先輩の足跡~