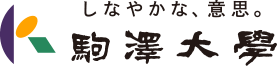令和6年度 学位記授与式(卒業式)総長祝辞
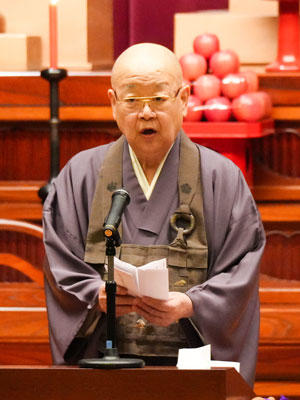 永井 政之 総長
永井 政之 総長
令和6年度3月の卒業式に当たり、学校法人駒澤大学の教職員を代表し、卒業生の皆さん、そして関係される保護者の皆さまに、お祝いの言葉を述べさせていただきます。
新型コロナウイルスに翻弄された5年余の時が過ぎ、令和5年5月、第5類の感染症に位置づけが変わった今、コロナ禍はすでに過去の出来事のような感すらあります。しかしこの度卒業される皆さんに即して見るなら、皆さんは貴重な学生生活の半分の歳月を、コロナ禍の中で送られました。
大学としてはできる限りの工夫努力をしたつもりですが、必ずしも十分であったとは言えません。
「研究と教育」、さらに友人関係構築の場にあって、多大な不便を被られた皆様に、大学を代表して衷心よりお詫び申し上げるとともに、皆さんがさまざまな工夫と努力の結果、ここに無事、卒業の日を迎えられたこと。心からお祝い申し上げます。
同時に、卒業後の皆さんが、遠い将来、青春を過ごした本学での学生生活を、どのように総括されるのか。その時が来るまで、時々刻々、変化する「ニューノーマル」の時間をどう過ごし、日本を、さらには世界を作り上げていくのか。私は強い関心と、そして期待を持っています。
考えてみれば、コロナ禍のトンネルは抜け出たかもしれませんが、解決すべき課題は山積しています。
戦争や不安定な経済の動向。近い将来、人間の能力を超えるであろうと想像されている「生成AI」の出現、さらに目的が達成されるにはまだまだ時間が必要に思われる、人類永遠の課題とも言えるSDGsの運動など。トンネルは尽きることがないと考えた方が無難のように思われます。
ここで確認すべきことは、未来がどのような時代になるにしても、それを構築する主体は、あくまでも「人間にある」ということ。そして毎日、毎日の私たち個々の営みが、未来の社会を作り上げているということを、忘れてはならないでしょう。
1年次の必修科目「仏教と人間」をはじめとして、さまざまな機会を通して理解されたように、駒澤大学は「仏教の教義と曹洞宗立宗の精神」を建学の理念とします。この「建学の理念」は、分かりやすく「信誠敬愛」や「行学一如」と表現されています。
この表現の背景に「日本の歴史」があることを否定できませんが、いずれにしても、「建学の理念」の言うところは、どのような人生を歩むにしても、ブッダの説かれた「縁起」の教えを学ぶ「智慧」と、あらゆる存在に対して、慈しみの心を持って生きていく「慈悲の心」を、人生の基本に置くべき、ということに外なりません。
「科学的思考」と「競争」を最優先に考えがちな現代です。歴史を見ればそれらが人間社会を豊かにしてきたことは否定すべくもありません。一方、それが、先ほど申したような、さまざまな問題を私達に突きつけていること、言うまでもありません。
言い古された感のある「人間疎外」という言葉の持つ意味が、より一層強くなったといったら言い過ぎでしょうか。
このように考えたとき、私は大本山永平寺を開かれた道元禅師が残された「自分自身(自己)と他人自身(他己)」という生き方を思い起こします。それは自分と自分以外のあらゆる存在を、同価値・平等であると見、お互いの尊厳を認め合う生き方を意味します。
また大本山總持寺を開かれた瑩山禅師は、「平常心是道」という言葉をもって悟りのきっかけとされたと伝えられます。この言葉は、文字通り、私達の普段の心のありよう、生活こそが、悟りの世界と言う意味ですが、それは禅で言うところの「修行」の考え方でもあります。
「禅」で言う「修行」とは、断食とか不眠不休とか、肉体を苛め抜くなど、何か特別のことを行うのではなく、「智慧と慈悲」を忘れることなく、毎日をつつがなく過ごすため、弛むことなく、努力を重ねていくこと。それが修行であり、普段の生活をそのように「営む」ことが、仏の世界そのものだと教えます。
皆さんのこれからの長い人生、予想できないこと、思い通りにならないことが、頻出することは疑いありません。そのような場合、どう工夫し対処するか。そんなとき「智慧と慈悲」という教えを、また「毎日が修行である」という教えを、是非、思い起こして頂きたく思います。
そのことを切に念じて、皆さんの卒業に当たっての、私のはなむけの言葉といたします。
令和7年3月吉日
学校法人駒澤大学
総長 永井 政之