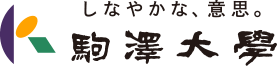久保 尚也(文学部心理学科)
「ハトは労力をかけることを好むのか?―労力選好に関する基礎研究の話」
令和4年度第4回祝祷音楽法要文化講演
(2022年10月14日)
本講演では、待ち時間に不要な労力をかけることを好む傾向に関する研究の話を行った。講演の構成は、『行動研究における労力について』、『ハトを対象とした実験的検討』、そして『労力に関する研究の展望について』の3つのパートに大きく分かれていた。
『行動研究における労力について』のパートでは、労力の相反する2つの側面について話がなされた。一方は労力が嫌悪されるという側面、他方は労力が好まれるという側面であった。前者については、同じ500円が得られるボタンでも、10回押して得られるAボタンと500回押して得られる B ボタンでは、多くの人は当然 A ボタンを選択するという例をもとに解説がなされた。ここでは労力には嫌悪性があり、ヒトを含めた生体には労力のかかることを避ける傾向が備わっていることが紹介された。後者の側面については、実社会でみられた事例と研究事例をもとに、あえて労力をかけることを好む現象について解説がなされた。実社会の事例としてあげられたのは、ヒューストン空港が行った"手荷物受取までの待ち時間が長い"というクレームへの対策事例で、手荷物が出てくるまでの間、利用客をあえて歩かせるという工夫によりクレームが減少したというものであった。研究事例は、ヒューストン空港の実例を模擬的に構成した実験課題を使用し、ハトを対象に行った研究であった。これらの研究は、エサの提示までただ待つだけの選択肢と労力の伴う行動が要求される選択肢の2つを設定した場面間の選択課題を用いた研究で、一部のハトが労力の伴う選択肢への選好を示す結果がえられているという話がなされた。
次の『ハトを対象とした実験的検討』のパートでは、実際の実験映像などを交えながら、本学にて3羽のハトを対象に行われた研究の概要が紹介された。この研究は、待ち時間にあえて労力をかけることへの選好が、待ち時間全体において占める、労力の伴う行動に従事していた時間の割合によって変化するか検討した研究であった。手続きおよび結果の概要は次の通りであった。実験課題として先行研究と同様、エサが提示されるまでの待ち時間が等しい、2つの選択肢間の選択課題が採用された。一方の選択肢は、ただ時間経過を待つだけの選択肢(wait リンク)であった。他方の選択肢は、労力の伴う行動として20回のキーつつき反応が最初に要求され、キーつつき反応完遂後に待ち時間が挿入される選択肢(effort リンク)となっていた。実験条件としては、後者の選択肢におけるキーつつき反応完了所要時間が占める、待ち時間全体の割合を操作した。条件として設定された割合は、40 %、60 %、80 %の3条件であった。実験の結果、1羽は、80 %条件において effort リンクへの選好を示し、残りの2条件ではただ待つだけの wait リンクへの選好を示した。残りの2羽は、すべての条件において wait リンクへの選好を示した。これらの結果をもとに、不要な労力を好む傾向はハトにおいても備わっている可能性があるが、この選好には個体差が大きい可能性があることが報告された。
最後の『労力に関する研究の展望』では、次の2点が示された。ひとつは、労力には嫌悪性だけでなく、行動や刺激に与えるポジティブな効果があるのではないかということであった。もうひとつは、労力のもつそのポジティブな効果について研究を行うことで、ヒトの行動を理解していくうえでは重要ではないかという点であった。