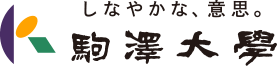王 穎琳(経済学部経済学科)
「中国紡織機械製造業の基盤形成―技術移転と西川秋次」
令和6年度第4回祝祷音楽法要文化講演
(2024年9月16日)
中国紡織業が中国経済の発展とくに外貨獲得に果たした役割はきわめて大きい。1959年に5億7,000万人の衣類の需要が満たされた。綿工業の自給化を支えたのは紡織機械の国産化である。解放前の中国綿工業は輸入紡織機械に依存していたが、新中国の紡織機械製造業は1957年までに国内紡織工場の需要を満たしただけでなく、一部の紡織機械を輸出した。中国紡織機械の自給化に関する実証研究は、これまで資料およびイデオロギーの制約のためほとんど進展しなかった。本報告は中国紡織機器製造公司(以下、中機公司と略す)の設立および事業展開のプロセスを考察し、西川秋次をはじめとする豊田の日本人技術者の技術協力の実態を解明する。
西川秋次の兄は豊田佐吉の夫人と遠縁の間柄であった。名古屋市の師範学校を卒業した西川秋次は豊田佐吉の勧めを受けて、東京工業大学の紡織学科へ進学した。1919年に豊田佐吉は自分の発明した自動織機を中国で現地生産しようとし、西川秋次を伴って、上海に渡り、紡織工場の設立と経営を西川秋次に一任した。その背景には、中国の関税引き上げと日本の深夜業禁止のため、日本の有力紡績会社は製造コスト削減のために、揃って深夜業が自由に行える中国へ進出したことがある。また、発明に必要な資金を他人に仰いだために失敗した佐吉にとって、上海進出は自動織機の研究資金を得るための手段でもあった。
1920年に、豊田紡織厰が上海で稼働した。西川秋次は事実上の最高責任者であり、豊田紡織廠を25万錘保有する大企業に育てあげ、機械、自動車、ゴムなどの事業にも進出した。また、西川は豊田佐吉や豊田喜一郎の自動織機と自動車開発の資金を援助した。1936年5月29日に公布した「自動車製造事業法」により豊田自動織機製作所は軍用トラックの生産に進出したが、資金不足であった。西川秋次の決断で豊田紡織厰は300万円を出資し、トヨタ自動車工業株式会社の設立に寄与した。日本では戦争物資動員のため、織機や自動車の製造ができなくなった。「部品の現地自活を」するため、1942年2月に西川秋次はトヨタ自動車工業の軍用トラックの修理を目的とする華中豊田自動車工業株式会社を設立し、12月に紡織機械の修理・製造・販売を目的とする豊田機械製造廠を設立した。さらに、終戦によって豊田紡織廠の物的資産は失ったが、登録国債(724万円)などの貨幣資産が残った。西川秋次は1950年8月に、豊田紡織厰の内地資産2100万円を日新通商に出資し、資本金を3000万円とし、豊田通商に社名を変更した。
第二次世界大戦後、日本在華紡織企業(以下、在華紡と略す)の全設備が国民政府に接収された。1945年11月27日に、行政院長の宋子文は在華紡を国有化し、中国最大規模の紡織企業である中国紡織建設公司(以下、中紡公司と略す)を設立した。主要な日本人技術者は現地で徴用された。西川は堀内干城公使を通じて、宋子文に「豊田の紡織技術を、復興中国に植え付けることによって、両国民間の友好関係が芽ばえ共存共栄の道が開けることと信ずるからである」という建白書を提出し、旧豊田在中国各工場の利用、豊田製品の特許使用権の利用、旧豊田技術者の任用という方法を提示し、志願で中国に残留した。当時、綿工業を中心とする経済発展が計画されており、紡錘や織機の増設が見込まれたため、宋子文は西川の提案を賞賛し、迅速に紡織機械製造会社を設立するように指示した。
1946年2月25日に「半官半民」の中機公司が設立された。西川にとって、紡織機械製造会社を中紡公司の傘下に入れるより、別会社のほうが、将来豊田自動織機製作所との技術交流をしやすいという考えがあった。「重要な部分を内地(日本)に仰ぎ、非重要な部分を貴地にて製作致す」と示されるように、西川は中機公司を「豊田産業の将来の仕事として」位置付けていた。一方、日本在華紡の国有化により民間紡織業者の不満を招いた宋子文にとって「民間紡織企業と利を争う」というイメージを払拭するために、西川案を受け入れ、政府の現物出資(40%)と民間紡織業の現金出資(60%)という形が好都合であった。
しかし、この計画が実行に移される過程で、内戦の激化による混乱や中紡公司との利害衝突によって、さまざまな障害が生じた。当初の西川計画は、中国にある豊田のすべての工場と在華紡の機械工場(合計10工場)を利用し、豊田紡織廠の収益で豊田機械製造廠の運営を支援し、中機公司を世界一流の紡織機械製造業者にするというものであった。ところが、この西川計画を受け入れた宋子文などの国民政府の高官は、国家財政が逼迫するなか、収益性の高い国有企業である中紡公司の利益を最優先した。中紡公司は豊田紡織廠、豊田機械製造廠、工作機械とG型自動織機の部品を大量に保有していた青島と天津にある豊田各工場を中機公司に譲渡しなかっただけでなく、中機公司に譲ることになった華中豊田自動車工業内の機械と機材を搬出した。また、中紡公司は豊田機械製造廠が保有した金型を中機公司に譲ることを拒否したうえで、織機と工作機械の設計図面の受け渡しも遅らせた。その結果、中機公司は華中豊田自動車工業、日本機械製作所第5廠、遠東鋼糸布廠を接収し、1946年10月1日に操業を開始したが、この三つの工場は紡織機械製造のために整備された工場ではなかった。中機公司は国策会社とされながらも、運営資金も民間株主の払込金に限られ、自力更生を余儀なくされた。
日本人技術者の指導のもと、工作機械の不足、資材の欠乏、治工具の製造、鋳造部品の品質改善、資金不足、製造経験のない中国人技術者と労働者などの難題を一つずつクリアした。その結果、Jαハイドラフト・G型自動織機の製造技術と生産管理方式が移転された。具体的には、第1に、「精密製造、大量生産」を方針とする中機公司は、紡織機械の量産化の基礎に当たる金型・砂箱・治工具・多種類の専用工作機械を内製し、鋳造設備を増設し、部品の標準化を実現した。第2に、西川は部品の番号付け制度、豊田自動織機製作所の各種作業表、事務連絡表、伝票を導入し、グループ改善活動を促進した。中機公司は1年間という短期間で、G型自動織機を月に200台製造する量産体制を構築したとともに、労働者数が1300人に達し、中国最大規模の織機メーカーとなった。こうした驚異的な発展には、生産設備にかかわる製造技術の移転、日本人技術者の指導が決定的であったとともに、紡織機械製造技術を主体的に学習した中国人技術者も重要な役割を果たした。
1949年3月に日本人技術者は全員帰国した。5月27日に上海が解放された。6月1日に中機公司は操業を再開し、中国最大の織機メーカーに成長した。中機公司の年間生産台数は1950年の1,968台、51年の4,111台、52年の6,300台に急増し、西川の初期計画の月産500台を実現した。すなわち、解放前のG型自動織機の量産化は、新中国の第1次五カ年計画期で達成された紡織機械の自給化に重要な技術的基盤を提供することになった。
中国紡織機械製造業の発展について、解放前と解放後を完全に断絶する考え方がある。しかし、中機公司の生産高が急増したのは、解放前からの連続した技術蓄積によってはじめて実現されたことである。紡織機械の図面や工作機械などの製造施設のような物的資源の存在のほかに、現場労働力としての中国人労働者の存在、日本人技術者と共同作業をしていた中国人技術者の存在のように、解放前から蓄積された人的資源の存在とその連続性は重要である。そのため、中国経済の発展のために中国に残り、貴重な技術移転を断行した西川をはじめとする豊田の日本人技術者たちの努力は評価すべきであろう。
本報告は『中国紡織機械製造業の基盤形成―技術移転と西川秋次―』(王穎琳著、学術出版会、2009年)を基礎にしたものである。