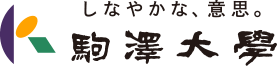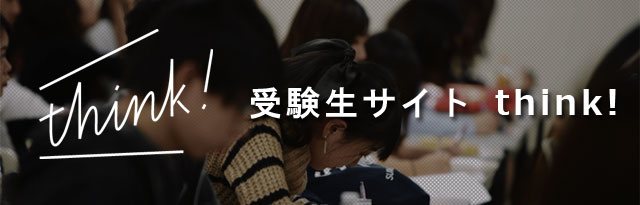~襷~ グローバルヘルスの「開拓者」 ~専門領域を基点に広げる医療実践~
【襷(たすき)】は、駒澤大学に通う皆さんが「どのような社会人生活を送りたいか」をイメージできる、キャリアセンター発の連載企画です。在学生が現在活躍する駒大OB・OGを訪問し、先輩たちのリアルな声をお届けします。
熊谷優季先輩に、経営学部4年 前谷が取材しました!(2025年3月取材)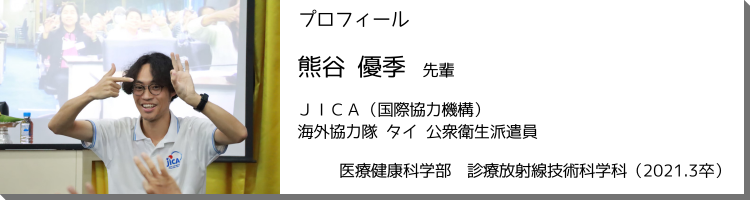
診療放射線技師への道
医療健康科学部を選んだ理由を教えてください
駒澤大学医療健康科学部は、大学内で唯一の理系・医療系学部です。診療放射線技師という病院で働く医療職を目指す学科で、X線(レントゲン)、CT、MRIなど画像診断の検査や放射線治療を担当する医療従事者を育成しています。
元々は自営業を営む不安定な家庭環境で育ち、その反面教師として安定した資格職で自立して生きていきたいという思いがありました。高校生の進路選択時に医療職が候補として浮上し、さまざまな選択肢を検討しました。
特に放射線という分野に惹かれたのは、中学生の頃の東日本大震災での経験が影響しています。当時、放射線の危険性について連日報道されるなか、自分で調べてみると「放射線」という言葉が記憶に残りました。高校時代に改めて調査すると、危険でありながら医療では不可欠な存在という放射線の二面性に興味を持ちました。さらに、診療放射線技師は資格職であり就職率も高いことから、大学で勉強する意義を見出せると感じたのです。
専門分野を選ぶことに不安はありませんでしたか?
ありませんでした。自分の選択肢を広げる手段だと考えています。医療系の資格は特定の学科でなければ取得できませんし、診療放射線技師は日本全体でも5〜6万人ほどしかおらず、2400人分の1(日本全人口に対して)の希少な人材になれる道です。これはニッチな領域で自分のオリジナリティを持って戦える可能性を意味します。
せっかく大学に行くなら、社会で役立つ専門的な知識や技術を習得したいと考えました。専門性を身につけることが、むしろ選択肢を広げると確信していたのです。
学生時代の探求
大学では主に国家試験対策に割く時間が多かったですか?
国家試験合格が前提とされていましたが、それだけでは物足りず、もっと面白いことを勉強したいという思いが強くありました。大学1年次から様々な授業や研究室を訪ね、先生方と対話を重ねました。
しかし、期待とのギャップも感じました。そこで大学の外に出て、学部や学科の枠を超えた学びを求めるようになりました。医療健康科学部は必修科目が多く、ハードなカリキュラムでしたが、外部活動との両立を試みた結果、単位不足に陥り、留年の危機に直面したこともあります。
休学という選択の背景を教えてください
大学2年と3年の間に1年間の休学を決意しました。留年は避けたいが、必修科目との両立が難しくなっていたこと、また自分のやりたいことを集中してやりきりたいという思いからでした。
この決断の背景には、幼少期から感じていた情報格差や社会の不条理への問題意識がありました。小学校時代に中学受験という世界を知った時の驚きや、教育環境の違いによって人生が大きく左右されることへの疑問が、自ら常に情報を取りに行く、習慣にも近い行動力につながりました。休学も、自分の人生を自分で選択するための決断でした。1年間やりたいことをやり切った上で戻ってきた方が、残りの学生生活に集中できると考えたのです。
休学中はどのように過ごしていましたか?
休学中は半年間、日本の様々な地方を巡り、残りの半年は海外で過ごしました。大学1、2年次から様々な先生方にお世話になり、海外の学会にも参加する機会があったため、長期間海外で過ごしたいという願望が強くなったのです。
東京出身で地方への憧れもあり、国内の様々な地域を訪れました。また、海外での長期滞在を通じて異なる文化や医療制度、放射線技術の活用状況などを実際に見て学びたいと考えていました。
ただし、放射線学科の学生としてのつながりは維持し続け、学科のイベントには参加し、海外からの学生のアテンドも担当しました。休学は辞めるということではなく、やりたいことを思う存分できる期間として活用したのです。



キャリア形成への挑戦
卒業後の進路はどのように決めたのですか?
卒業後の進路を考える際、海外で働きたいという思いが強くありました。東南アジアを中心に国際協力の経験もあり、そうした人々と一緒に働きたいと考えていました。
最短で海外での実務経験を積む方法を模索した結果、JICAの海外協力隊というプログラムに注目しました。しかし、診療放射線技師としての募集案件はほとんど無かったので視野を広げ、公衆衛生という分野であれば案件が増えることがわかりました。
公衆衛生を学ぶためには勉強し直す必要があったため、大学院進学も視野に入れていました。しかし、大学4年次にコロナ禍が到来し、海外渡航が困難になりました。そこで、まずは国内の病院で経験を積みながら、次のステップへの準備をすることにしました。
大学院進学と病院勤務の両立の裏側を教えてください
公衆衛生学を学べる大学院に進学し、同時に同大学の附属病院で診療放射線技師として働く道を選びました。修士課程では、日中は病院でフルタイム勤務し、夕方から大学院の授業を受けるという二足のわらじを履いていました。
この選択には二つの理由がありました。一つは、コロナ禍での医療現場の状況を直接経験したいという思い。もう一つは、将来の国際活動のための準備として、臨床経験と学術的知識の両方を身につけておきたいという考えでした。
当時通っていた大学院には附属病院が隣接していたため、両方を行き来しやすい環境でした。また、駒澤大学の放射線学科は思っている以上に歴史が古く、卒業生の方が病院の要職に就いていらっしゃいました。その繋がりから勤務の機会を得ることができたのです。
コロナ禍でも海外活動の機会があったそうですね?
修士課程在学中にも、コロナ禍にもかかわらず海外での活動機会がありました。カンボジアで3ヶ月間ボランティア活動をしたり、中央アジアでのプロジェクトに参加したりしました。コロナ禍で海外に行ける医療従事者が少なかった中、診療放射線技師としての実務経験と国際保健・公衆衛生の学びを両立していた稀少な人材として声がかかったのです。
病院勤務と大学院での学びを両立させていたことで、臨床技術と公衆衛生の知識を持つ珍しい存在となり、海外プロジェクトでの需要が生まれました。特に中央アジアのプロジェクトでは、放射線機器の取り扱いができる医療従事者が必要とされており、貴重な経験を積むことができました。
これらの国内外での経験が現在の活動につながっており、様々なご縁やタイミングが絶妙に合致して今に至っています。現在は、JICAの海外協力隊員として活動しながら、大学院の博士課程で学び、さらに駒澤大学医療健康科学研究所の客員研究員という3つの肩書きを持っています。



現在の活動と課題
タイではどのような課題に取り組んでいるのですか?
現在タイで取り組んでいる課題は高齢化社会への対応です。東南アジアでも急速に高齢化が進んでおり、特に北部のチェンマイ地域では多くの高齢者が劣悪な環境で暮らしています。
歩行困難で自力で病院に行けない高齢者が多く、地域の看護師や保健ボランティアが定期的に見回りをしている状況です。脳梗塞で半身麻痺になった方や、自宅で十分なケアを受けられない高齢者も少なくありません。
日本と比較すると、タイの高齢化率の上昇カーブは急激です。しかし、政府の仕組みや保険制度、介護人材などの体制が整っていません。リハビリや介護の専門施設も少なく、経済的に余裕のある人しか利用できない状況です。
どのような解決策に取り組んでいますか?
タイの課題に対しては、コミュニティの力を活かした解決策が有効だと考えています。タイには「プライマリーヘルスケア」という考え方が根付いており、コミュニティで医療や健康を支援する文化があります。例えば、LINEなどのアプリを活用したコミュニティ間のコミュニケーションを促進し、地域で高齢者を見守る体制を強化する取り組みを行っています。タイは日本より先にLINEの普及が進んだ国でもあり、テクノロジーを活用した繋がりづくりが可能です。
技術や設備だけでなく、それをどう届けるかというシステムやコミュニティの力が重要です。目指しているのは、医療や保健サービスが届いていない場所に届けることであり、そのために橋渡し役として活動していきたいと考えています。


日本の医療と比較してどのような違いがありますか?
日本の医療は技術的には進んでいますが、テクノロジーの導入が遅いという課題があります。例えば電子カルテの普及率は日本では55%程度で、特に地方の診療所等ではまだまだ紙ベースの管理が主流です。一方、東南アジアなどでは国が決めれば一気に最新技術が導入されることもあります。
また、日本では医療費の高騰や病院経営の困難さという問題もあります。しかし、皆保険制度により基本的な医療へのアクセスは確保されているため、危機感が薄い面もあるでしょう。タイなどの新興国では、発展段階にあるからこそ、最新技術を一気に導入できる「リープフロッグ現象」が見られます。日本で10年かけて導入されるような技術が、他国では数年で普及することもあるのです。地球規模で考えれば、発展途上にある医療システムにアプローチすることで、より多くの人々の健康に貢献できる可能性があります。
未来への展望
今後の目標を教えてください
医療が届いていない場所に医療を届けていく活動を続けることです。保健医療や健康が行き届いていない地域に、それらを届けていくことを長期的な活動テーマとして考えています。
現在タイでの活動は2025年8月に終了予定で、その後の予定はまだ決まっていませんが、博士論文執筆が当面の課題です。博士号取得でキャリアの幅が広がり、より多くの国際的な活動ができるようになります。今できることを優先し、将来の展開はご縁やタイミングに委ねる部分もありますが、どんな機会にも対応できるよう準備していきたいと考えています。
私にとって仕事と遊びの境界線は曖昧です。現地の人々との交流はタイ語の勉強になり、新たな繋がりが協力関係に発展することも多いです。「遊び」と「活動」が融合している状態が理想的だと考えています。
学生へのメッセージ
医療と教育の可能性は無限大です。大学ではどの学部に所属しているかよりも、その環境で何を学び、どう活かすかが重要です。駒澤大学には様々な分野の素晴らしい先生方がいますので、学部や学科の枠を超えて積極的に交流してください。
駒澤大学で「できないこと」を嘆くのではなく、「できること」をたくさん見つけることが大切です。大学時代の4年間は自分次第でいかようにも活用できる貴重な時間です。
キャリアは直線的に進むとは限りません。重要なのは、自分の専門性を持ちながらも、視野を広く持つことです。どんな環境でも学ぶ姿勢を忘れず、新しい可能性に対して開かれた心を持ってください。自分が心から打ち込めることを是非見つけてください。今この瞬間に自分が成長できる環境にいるかどうか、それが本当の豊かさだと思います。
おわりに~インタビュアーの感想~
熊谷先輩のキャリアは、専門性を軸にしながらも、常に新しい可能性を模索し続ける姿勢が印象的でした。診療放射線技師としての知識と経験を活かしつつ、公衆衛生や国際医療の分野へと挑戦を広げていく柔軟性は、まさに「選択肢を広げる生き方」の実践そのものだと感じました。特に、留学や休学を通じて自ら学びの機会をつくり、海外での医療支援に挑戦している点は、私自身の将来を考える上でも大きな刺激になりました。
熊谷先輩のように、自分の専門を深めつつも視野を広げ、社会に貢献できるキャリアを築いていきたいと強く思います。

[著]・[聞] 経営学部 経営学科4年_前谷悠太
[写] 熊谷先輩より提供していただきました
※記事の内容は取材時点のものであり、最新の情報とは異なる場合があります。
※本記事掲載写真は、無断での転載・使用はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
本記事関連リンク
JICA(国際協力機構)
駒澤大学医療健康科学部診療放射線科学科
医療健康科学研究所 学生研究員 取材企画「先輩に訊く!」
Japan Heart カンボジア 熊谷活動レポート
診療放射線技師100人カイギ(熊谷先輩が発起人として立上げ)
∟ YouTube ∟ 100人カイギの取材記事
デンマーク留学ヒッチハイク時の記事
襷~先輩の足跡~