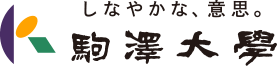平成28年度 入学式 学長式辞


新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。桜は満開から葉桜となり、いよいよ新緑の好時節に、私たちは皆さんを本学の新たな一員としてお迎えできますこと、この上ない喜びであります。また、このよき日を迎えられましたご列席の保護者の皆様にも心よりお祝い申し上げます。
また、大学院に入学された皆さんにも、お祝い申し上げます。学部時代に身に付けた学問を一層深められ、その学問がよりアクティブなものとなり、司法試験あるいは臨床心理士試験等の資格試験に備えられるよう精進してください。
社会人入学の皆さん、ご入学おめでとうございます。皆さんの旺盛な学習意欲に、甚深なる敬意を表します。大いに、駒澤大学を満喫していただきたいと思います。
新入生の皆さん、この緑豊かな静かなキャンパスで、ゆったりと構え、勉学に励んでください。本学は7つの学部と8つの大学院がこの駒沢のワンキャンパスに所在し、1万5千の学生が専門科目はもとより、多種多様な分野の学問に触れることができ、互いの顔が見える大学です。
皆さんの将来は、この4年間にかかっていると言っても過言ではないでしょう。どれだけ専門的な学問を修め、どれだけの調査研究ができるようになるか、それをいかに豊かなプレゼンテーションに繋げうるのか、立派な卒論やレポート作成に持って行けるのか、これらが問われることになります。また、さまざまなスキルの修得も必要です。英語を中心とする語学の能力を高め、TOEIC・TOEFLの点数アップ、それぞれの分野の資格取得にもチャレンジしてください。
大学では、自らの努力次第でいくらでも高い能力を身に付けることができます。皆さんは同じスタートラインに立ったのです。
皆さんが、禅・仏教の大学、駒澤大学で学んだことは、将来の就職の時に、あるいは海外に出た時などにも役に立ちます。就職の面接の時に駒澤大学で学び、坐禅を組んだことがあるなどのことを発言しましたなら、注目を集め、他大の学生に比べ俄然有利に立つことでしょう。海外でも禅のことを口にしましたなら、様々な面で役立つことになります。ただ、質問を受けますので、一通りのことは在学中に勉強しておいてください。この点は、本学のカリキュラムに組まれておりますのでご安心ください。
グローバル社会の中で、クールジャパンとしてアニメや日本製品、あるいは日本文化、和食などが注目を集めていますが、能・狂言・歌舞伎、茶の湯、枯山水・水墨画などの日本を代表する文化の底流には、禅の精神が流れています。それゆえに禅は世界から注目を集めているのです。コンピュータ囲碁で優勝を重ねている頭脳エンジンに「ZEN(禅)」という名称がつけられているのも、禅が世界的に注目されている証左です。
ここで、駒澤大学が如何に魅力的な大学であるか、興味深い歴史・伝統・エピソードをもっているかを示しておきましょう。本学は、我が国はもとより世界的に見ても、最も長い歴史と豊かな伝統を持つ大学のひとつです。江戸城を造り江戸東京の祖として知られ、武人としても歌人としても名を馳せた太田道灌が、城の近くに駒澤大学の前身の前身である吉祥寺を建立したことに始まります。およそ555年前のことです。その後、徳川家康が江戸城に入って間もないころ、1592(文禄元)年、その吉祥寺の中に本学の前身の学寮旃檀林ができました。424年前のことです。
ところが、江戸時代前期の1657(明暦3)年、江戸の大半と江戸城天守閣を焼き尽くした振袖火事により旃檀林は駒込へ移転します。
駒込に移った旃檀林は禅学と漢学の学問を中心に修め、東京大学の前身である幕府の昌平坂学問所と競い合ったといわれています。
そして、1882(明治15)年、麻布北日ヶ窪の地に近代的な大学として出発しました。現在の六本木ヒルズ・テレビ朝日のところです。そこから駒沢の地に移転してきて103年です。移転当時は隣に日本人が初めて造成したというゴルフ場があるだけであったといいます。本学は4年前に開校130周年、3年前に移転100周年を迎えました。
本学で一番古い建物は禅文化歴史博物館で、1928(昭和3)年に建造された建物です。東京都歴史的建造物となっています。設計者は菅原栄蔵という人物ですが、この人物が設計したものにレンガ造りの銀座ライオンがあります。さらに、禅や茶の湯と関係深い建物に数寄屋造りがありますが、深沢キャンパスの洋館はその数寄屋造りの要素を取り入れた設計で知られる吉田五十八のものであります。
なお、禅の大学らしさを一層深めるために、図書館前や記念碑の前に枯山水の石庭を造り、金閣寺垣や建仁寺垣の竹垣を施しました。これら枯山水・竹垣・プランターの花々は、工事中の安全とともに美化を図るという観点から設けています。
次に本学の建学の理念について示し、本学で学ぶ皆さんに期待するものをお伝えしたいと思います。永平寺を開いた道元禅師が示された最も重要な言葉に「修証一等」があります。すなわち、坐禅修行(修)と悟り(証)は一体である、悟りは遠い彼方にあるのではなく、坐禅する姿の中に現れるというのです。道元禅師の禅は、坐禅修行を積み重ねて悟りに至るというのではなく、年長年少にかかわらず誰でも坐禅の時に悟りがあらわれるとするのです。「行」を徹底して重要視し、悟り(証)と全く同等(一如・一体)としたのです。
本学は、この道元禅師の「修証一等」に基づく「行学一如」という言葉を建学の理念としています。行と学は一体であるとします。行とは自己陶冶のこと、学とは学問研究のことです、学問研究はアクティブな学、すなわち、行によって本当の学となり、自分の血となり肉となるのです。「学」に支えられた「行」の実践の重視ともいえます。
また、禅の言葉に「随処に主となる」という言葉があります。いかなる場所や状況にあろうとも、人のあとからついて行くのでなく、常に自分のできることは何かを考え、主体的に考え、行動できる人になってください。
また、道元禅師には『典座教訓』という書があります。典座(てんぞ)とは、禅寺の料理長のことですので、料理長の心得の書ということになります。この中に中国の典座とのエピソードが書かれています。天童山という寺で修行していた真夏のある日、この寺の典座が焼けた敷き瓦の上に、汗をもかまわずきのこを晒していた。いかにも苦しそうだ。年齢を問えば68歳だという。道元禅師が、なぜ若い人にやらせないのか、この炎天下でやらなくてもよいのではないかと言うと、「他はこれ吾にあらず」、人は人、自分がやらないで誰がやるのか、「更に何れの時をか待たん」、時は人を待ってくれない、今やらないで何時やるのか、今が大切なのだと言われてしまったというのです。
さらに道元禅師はその著書『正法眼蔵』の中で、「而今(にこん)」ということを述べておられます。今が大切、今が大事ということです。考えてみれば、私たちは、何時も今にしか生きていません。「またこの次、またこの次」という先送りは、問題の本質的な解決にはなりません。やはり今が大切です。皆さんも「今を大切に」一生懸命に勉学に励んでください。
最後にお断りしておかなければならないのは、開校130年記念棟建設中に皆さんをお迎えしたことです。しかし、おかげさまで工事は順調に進んでおり、あと1年と9ヶ月でメインタワーが完成します。9階建で広大な駒沢公園の緑に視界が広がる、明るい建物になります。PC教場やグループ学習室、多目的ホール、現在よりはるかに広い食堂ができます。皆さんは第3学年からこの新しい校舎で学ぶことができます。
これまで縷々述べてまいりましたが、本学には興味深いエピソードがあり、魅力に満ちております。このような環境の中で皆さんは大学生活を送ることになります。
また、皆さんは「行学一如」「随処で主となる」「而今」の精神で、「禅のこころで人を育む」この駒澤大学で人間力・総合力を高めていってください。一回りも二回りも大きな人間に成長されますことを期待しております。
どうぞ、大いにキャンパスライフを謳歌してください。
本日は誠におめでとうございます。
平成28年4月8日
駒澤大学 学長 廣瀬 良弘